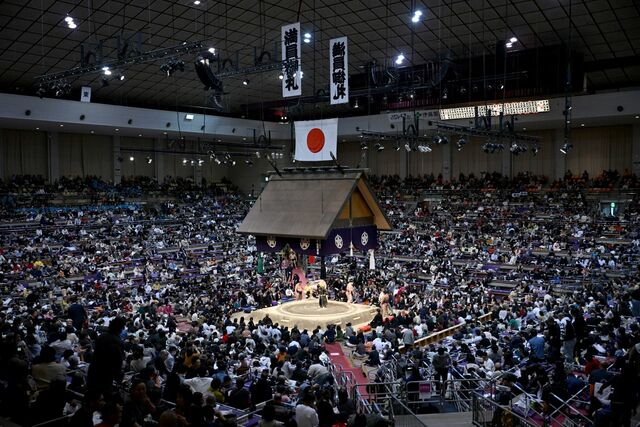久しぶりのPC自作
ここのところ、担当のブログ更新が多忙を極めて滞っていました。責任持って仕事しないといけないのに、困った奴です>店長。
長らくCPUに「AMD Ryzen 5 2400G」を使った自作のパソコンにUbuntu(Linux)をインストールして使っていました。会社の各種データは Windows マシンが前提で構成されていますので Windows11 を利用もしていますが、その他のWeb作業、画像処理、動作処理、そしてプログラム作業はほぼUbuntuでしています。
そのマシンですが、CPUとしての基本性能はぼちぼちなのですが、内蔵グラフィックチップのバージョンがやや古くて、いつからかドライバーのバージョンアップができなくなりました。それでも上手く動いていれば困らないのですが、大規模な画像などを処理していると、時々ブラックアウトしてしまうのです。1秒くらいブラックアウトしたのち、何事も無かっ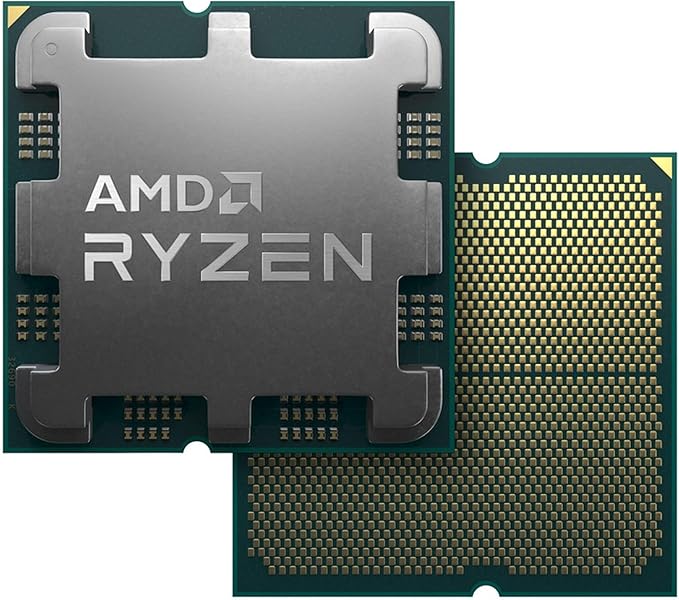 たように画面表示されて作業が続けられます。でも、文を書いているとき、プログラムを書いているとき、WordPressのようなコンテンツ系の作業をしているときの画面の瞬断はものすごく作業の障害になります。
たように画面表示されて作業が続けられます。でも、文を書いているとき、プログラムを書いているとき、WordPressのようなコンテンツ系の作業をしているときの画面の瞬断はものすごく作業の障害になります。
原因は明らかで、最新のLinuxカーネルと古いドライバーの相性が悪くなってきているからです。AMD系のRadeonのLinux用ドライバーはオープンソースで開発されていて、古いハードとの互換性はあまり考慮されていません。これは Nvidia系でも思想は同じでこちらはオープンソースではないですがAI向けGPUに開発リソースが割かれていて、ユーザー数の少ないLinux系GUIデスクトップ用ドライバーまで中々手が回らないのでしょう。
ということで最も簡単な解決策はハードの更新です。店長は基本的に別途グラフィックカードを使わずCPU内蔵型のGPUを使います。予算の許す限りの範囲で、できるだけ最新のCPUを使うようにしています。AMDの場合は、CPU型番の最後にGがついているのがグラフィックチップ内蔵型のCPUです。
 今回は「AMD CPU Ryzen 7 8700G」を使いました。そんなに高性能なCPUではありませんが、ゲームなどしないユーザーにとってはハイエンドといえます。文を書いたり画像や動画を処理したりなどには十分に高速です。グラフィック周りのドライバーもしばらくは安定して更新できると思います。
今回は「AMD CPU Ryzen 7 8700G」を使いました。そんなに高性能なCPUではありませんが、ゲームなどしないユーザーにとってはハイエンドといえます。文を書いたり画像や動画を処理したりなどには十分に高速です。グラフィック周りのドライバーもしばらくは安定して更新できると思います。
今回はケースと電源は変更せず、CPUとメモリーとマザーボードを変更しました。ケースは10年以上前の AOPEN XCcube という小型卓上PCのケースを mini-ITX マザーボードが使える様に改造したものです。特徴は、ケース内の天地サイズが大きく取れるのでCPUファンも比較的大きなものが使えます。このCPUは消費電力も少ないので、電源は400WのSFXをそのまま使いました。メモリーは16G(DDR-4)から32G(DDR-5)にアップグレードしました。HDDは買い換えずそのままNVMeタイプを利用しました。古いマシンではいわゆるBIOS起動で最新のEUFIではなかったようです。買ったマザーではUEFIが必須のようで、あわよくばそのまま立ち上がるかという思惑が外れて、新たにUbuntu24.10Desktop をインストールしました。店長はデータは徹底的にバックアップを取っているので、アプリケーションだけインストールすれば、多少時間がかかりますが困ることはありませんでした。
この文も新装マシンで書いていますが、文はGoogleドキュメントで書き推敲していきます。これのメリットは、保存動作(バックアップ処理)は必要ないこと、ネットにつながっているマシンからならスマホでもタブレットでもPCでも、いつでもどこでも作業ができることです。実際、店長もなかなか時間が取れないときは、ちょっとした待ち時間とかに推敲しています。マイクロソフトのオフィスでないと各所、各団体との互換性がとか頭カチカチのことを言う人がいますが、実際に困るのは印刷の寸法合わせとかだけで内容の読み書きなど全く困りません。実際、印刷の頻度も本当に少なくなってきているので店長はこれで十分です。どうしても印刷の互換性がとか言う場合は、PDF形式にして保存します。外部からの文書などもPDFで送ってもらう様にしてもらったら困りません。
自作マシンは、部品だけの交換でアップグレードできる余地があります。最近のCPUは消費電力(≒TDP)が低いので電源の使い回しは難しくありません。とは言っても今回はCPUとメモリーとマザーボードを変えましたが、費用は近い性能のCPUを使っている場合の3割程度安価に上がると思います。今まで、何十台というPCを組み立ててきましたが、動かなかったことは一度もありません。仕事用のPCですから趣味で組み立てということではありませんが、小規模オフィスにオーバースペックな性能のサーバーを導入を勧められてる等の事例を聞くたびに、自分で作って簡単な無停電電源と日々のバックアップをしておけば悩む必要はないのになと感じています。PCの組み立ては部品さへ揃えられればプラモデルより簡単です。部品の調達はインターネットで簡単。楽しいことは積極的にしてみましょう、というオチで今回は終わります。