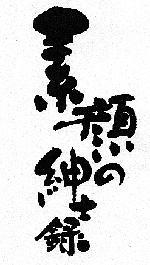 |
戦傷の不運を乗り越える 『素顔の紳士録』よりー2− 弊社21周年記念事業の一環として写真集『素顔の紳士録』を発刊した。大阪在住の写真家・生原良幸氏の撮り下ろした大阪のリーダー34氏の素顔と、各氏にかかわる私(折目)のエッセイで構成しているが、それは34氏から学んだ私の人間学の集大成でもある。そこで、前回に続き、『素顔の紳士録』から学んだ人間学を連載したい。 |
南京・棲霞山(せいかざん)に雲谷禅師を訪ねた袁了凡の姿を見て、禅師は興味ありげに彼を招き入れる。
「あなたは、お若いにもかかわらず泰然自若としていて、悟り得た風貌をしておられる。これまで、どのような修行をなさっておられたのか?」
聞かれるままに了凡は答える。
「とりたてた修業は致しておりません。ただ家業の医者になるべく勉強していた子供の頃、ある日偶然にある老翁と出会った。数を試みる(運勢を見る)その方から、君は仕路(官吏)に就く運命にあり、何歳で進士試験に受かり、何歳で役人になり、どこまで立身出世して、何歳で死ぬ。しかし子宝には恵まれない、と言われた。これまでの人生はその老翁の占い通りになっている。つまり人間は進むも退くも運命が決まっている。それを知った時、ああもしたい、こうもしたいという欲が無くなってしまった」
それを聞いた雲谷禅師は「なんだ、そんな事か。それなら君は大馬鹿者だ」
と一喝し、運命について語り出す。
「その老翁に占われて考えてきたようなことは、決して運命というものではない。本当の運命とは我より立つる、立命でなければならぬ」
雲谷禅師に懇々と諭されて、了凡は愕然とし、そして自らの考え方を一変させる。そしてそれからは一心に修業に励むのだが、そうすると、それからの人生は老翁の予言がことごとく外れるようになり、できないと言われた子供も生まれるし、死ぬと言われた年齢を過ぎても死なない。そこで初めて迷いを脱するのである。(引用文献『運命と立命ー陰隲録 安岡正篤先生講録』 関西師友協会刊)
運命を理解するに通常2タイプがある。
1つは、「運命、そんなものは迷信だよ」と全く無視する見方。学者やインテリと称される人達に多い。もう1つは、「これも運命というもの、仕方がない」と逆にこだわったり、言いわけにする見方である。
しかし、「本当の運命というのは、我から立つる立命でなければならない」とは素晴らしい言葉である。そう理解すると、決して迷信でもなければ、それぞれの人生に絶対的に重くのしかかる宿命でもない。文字通り自ら命を運ぶものであることが理解できる。
同書に推薦文を寄せていただいた住友生命保険の新井正明名誉会長の人生はその最たるものである。
新井さんは入社1年目の昭和13年1月に入隊、昭和14年8月のノモンハン事変でソ連軍の砲弾の直撃を受ける。一命はとりとめたものの右足を失う。
これも自分に与えられた運命かと、大概の人は考えるだろう。避けることのできない兵役である。そして新井さんも、戦地の病院から会社に辞表を提出する。 それに対して最高幹部から「辞めなくてよし、早く健康になり出社すべし」の電報が届く。そして日本に送還され入院した病院に電報の主、北澤敬二郎専務が見舞いに訪れ、「健康になり次第出勤するように。足が悪いのだから、遅く出勤して、早く退社することを認めよう」と言われる。
大変な感激であったと述懐し、著書にも書かれている。
だが実際の新井さんの勤務は、「足が不自由だからこそ、早く出社し、遅く帰る」毎日だった。我々の想像の到底及ばぬ心の葛藤を乗り越え、ままならぬ肉体との戦いを続けたはずである。
その1日1日の積み重ねが昭和41年、53歳での社長就任に繋がり、関西財界随一の存在感ある財界人を生み出していく。
もしその時、新井さんがノモンハンでの戦傷を運命としてとらえていたら、傷痍軍人としての人生が待っていたかもしれない。また復職後も、北澤専務の言葉に甘え、「遅く出社し、早く帰宅する」会社生活を積み重ねていたら、社長どころか、役員としての新井さんもいなかったろう。
友人の励ましもあった、会社の上司の理解もあっただろう。多くの古典や安岡正篤師との出会いもあった。それらのすべてから新井さんは前向きに生きる力を得る。それこそが立命であり、自ら立てた運命であった。
=つづく=